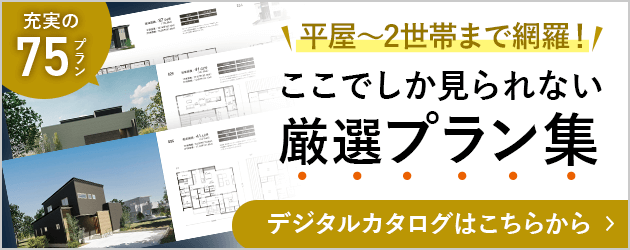吹き抜けのメリットとデメリットとは? おしゃれな実例もご紹介!
吹き抜けのある家は開放感がありデザイン性も高く、多くの魅力にあふれています。
しかしその一方で、知っておくべきメリットとデメリットが存在します。
吹き抜けの家を建ててから後悔しないためには、両方を正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合っているかを見極めることが欠かせません。
この記事では、吹き抜けの基本的な知識から、快適な空間にするための対策、そしておしゃれな実例までを分かりやすくご紹介します。
目次
- 【そもそも吹き抜けとは?】
- 【吹き抜けがもたらす3つのメリット】
・空間が広く感じられる圧倒的な開放感
・自然光が差し込み室内全体が明るくなる
・家族の気配を感じやすくなりコミュニケーションが円滑に
- 【吹き抜けで後悔しがちな4つのデメリット】
・冷暖房が効きにくく光熱費が高くなる
・料理の匂いや生活音が2階まで広がりやすい
・高い場所の窓掃除や電球交換が大変
・2階部分のスペースが狭くなる
- 【デメリットを解消!吹き抜けで後悔しないための対策】
・高気密・高断熱の住宅性能で室温を快適に保つ
・シーリングファンを設置して空気を循環させる
・メンテナンスしやすい窓や照明器具を選ぶ
・間取りを工夫して生活音や匂いの問題を軽減する - 【吹き抜けに関するよくある疑問】
・吹き抜けのある家は耐震性が低い?
・吹き抜けを作ると建築費用が高くなる? - 【おしゃれな吹き抜けの事例を場所別に紹介】
・開放感あふれるリビングの吹き抜け実例
・明るくおしゃれな印象になる玄関の吹き抜け実例
・階段スペースを有効活用した吹き抜け実例 - 【まとめ】
そもそも吹き抜けとは?

吹き抜けとは、建物の内部で、複数階にまたがって天井や床を設けず、上下がつながった大きな空間のことを指します。
具体的には、1階部分の天井と2階部分の床をなくして、1階から2階の天井や屋根までがひとつの空間になるような構造です。
この吹き抜けによって、縦方向に視線が抜け、空まで続くような広がりが生まれます。
一般的な家とは異なり、圧迫感のない開放的な空間を演出できるのが大きな特徴です。
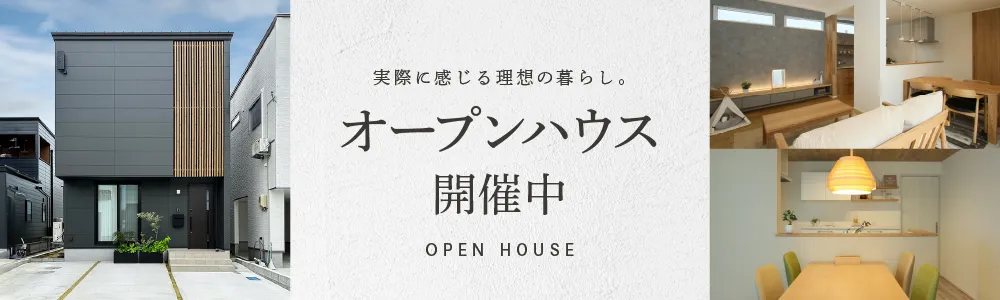
吹き抜けがもたらす4つのメリット
注文住宅で家を建てる際に、吹き抜けを取り入れるか悩む方は少なくありません。
吹き抜けには、デザイン性の高さだけでなく、暮らしを豊かにする多くのメリットがあります。
ここでは、吹き抜けがもたらす代表的な4つのメリットを解説します。
これらの魅力を知ることで、理想の住まいづくりに一歩近づけるでしょう。
注文住宅ならではの自由な設計で、吹き抜けの良さを最大限に活かす計画を立ててみてください。
空間が広く感じられる圧倒的な開放感

吹き抜けの最大のメリットは、なんといってもその圧倒的な開放感です。
天井高が高くなることで視線が縦に抜け、実際の床面積以上の広さを感じさせてくれます。
特に、土地の広さに制限があり、比較的コンパクトな家を建てる場合でも、吹き抜けを設けることで圧迫感を大幅に軽減できます。
例えば、リビングに勾配天井やスキップフロアを組み合わせれば、ホテルのラウンジのような非日常的でおしゃれな空間が生まれます。
たとえ小さな家であっても、吹き抜け一つで空間の印象は大きく変わり、ゆとりのある暮らし心地を実現できます。
自然光が差し込み室内全体が明るくなる
吹き抜けを設けることで、高い位置に窓を設置できるため、効率的に自然光を取り込めます。
1階のリビングなど、通常は光が届きにくい家の中心部まで明るく照らすことが可能です。
特に、南側など日当たりの良い方角に大きな窓を設ければ、日中は照明がなくても快適に過ごせるでしょう。
住宅が密集している都市部でも、高い位置からの採光は隣家の影響を受けにくいため非常に有効です。
夜には星空を眺められるなど、窓の向きや大きさ次第で暮らしの楽しみも広がります。
採光を重視するなら、吹き抜けは最適な選択肢の一つです。
家族の気配を感じやすくなりコミュニケーションが円滑に
吹き抜けは1階と2階をひとつの空間としてつなげるため、家族の気配を常に感じられるというメリットもあります。
例えば、1階のキッチンで料理をしながら、2階の子ども部屋にいる子どもの様子を感じ取ったり、気軽に声をかけたりできます。
音が伝わりやすいという特性は、家族間のコミュニケーションを自然に促してくれるでしょう。
別々のフロアで過ごしていても孤立感がなくなり、家全体に一体感が生まれます。
家族とのつながりを大切にしたいと考える方にとって、吹き抜けは暮らしの中心となる重要な空間になります。
吹き抜けで後悔しがちな4つのデメリット
憧れの吹き抜けを作ったものの、実際に住んでみてから「こんなはずではなかった」と後悔するケースも残念ながら存在します。
吹き抜けには、その開放的な構造ゆえのデメリットがいくつかあり、対策を怠ると快適な暮らしの妨げになる可能性があります。
ここでは、吹き抜けで後悔しがちな4つの代表的なデメリットを解説します。
冷暖房が効きにくく光熱費が高くなる

吹き抜けの大きなデメリットとして、冷暖房効率の問題が挙げられます。
暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降する性質があるため、冬は1階が寒く、夏は2階が暑いといった温度ムラが生じやすくなります。
これにより、家全体を快適な温度に保つために空調設備がフル稼働し、光熱費が高くなる傾向があります。
特に冬場は、大きな窓から熱が逃げやすく、結露の原因にもなりかねません。
対策として、住宅の断熱性能を高めたり、シーリングファンを設置したりするなどの対策が求められます。
料理の匂いや生活音が2階まで広がりやすい
空間が一体となっているため、1階で発生した匂いや音が2階まで広がりやすい点もデメリットです。
特に、リビングに隣接してキッチンを配置する場合、調理中の料理の匂いが2階の寝室やクローゼットにまで届いてしまうことがあります。
高性能なレンジフードや強力な換気扇を設置するなどの対策が欠かせません。
また、テレビの音や会話といった生活音も伝わりやすいため、就寝時間の異なる家族がいる場合や、静かな環境で集中したい場合には注意が必要です。
プライバシーを確保したい部屋の配置には配慮が求められます。
高い場所の窓掃除や電球交換が大変

吹き抜けの高い位置にある窓や照明器具は、日常の掃除やメンテナンスが大きな負担となることがあります。
窓をきれいに保つためには、柄の長いモップや高所用の掃除道具、あるいは安定した脚立が必要になり、作業には危険が伴うことも考えられます。
照明の電球が切れた際の交換も同様で、自分で行うのが難しく、専門業者に依頼するとその都度費用が発生します。
場合によっては、メンテナンスのために室内で足場を組む必要が出てくるケースも。
設計段階から、掃除のしやすさや電球交換の方法まで具体的に考えておくことが重要です。
2階部分のスペースが狭くなる
吹き抜けは、本来2階の床となる部分をなくして作られる空間です。
そのため、吹き抜けを採用すると、その分だけ2階の床面積が減少し、利用できるスペースが狭くなるというデメリットが生じます。
建築当初は問題なくても、将来的に家族構成が変化したり、子どもが成長して個室が必要になったりした際に、部屋数が足りなくなる可能性も考えられます。
限られた敷地面積の中で、吹き抜けの開放感と居住スペースの確保を両立させるためには、家全体の面積とのバランスを慎重に検討し、将来のライフプランを見据えた間取り計画が必要です。

デメリットを解消!吹き抜けで後悔しないための対策
これまで見てきたように、吹き抜けにはいくつかのデメリットが存在しますが、これらは設計上の工夫や設備の導入によって大部分を解消することが可能です。
ここでは、デメリットを克服し、吹き抜けの魅力を最大限に引き出すための具体的な対策をご紹介します。
扉の設置なども含め、計画段階でぜひ参考にしてください。
高気密・高断熱の住宅性能で室温を快適に保つ

吹き抜けの最大の懸念点である室温管理の問題は、住宅そのものの性能を高めることで解決できます。
具体的には、高気密・高断熱仕様の家を建てることです。
気密性が高い家は隙間風が少なく、断熱性が高い家は外の暑さや寒さの影響を受けにくいため、室内の温度を快適に保ちやすくなります。
これにより、吹き抜けのような大きな空間でもエアコンの効きが良くなり、冷暖房効率が向上します。
初期費用はかかりますが、長期的に見れば光熱費を抑えることにもつながり、一年中快適な室内環境を維持できます。
シーリングファンを設置して空気を循環させる
吹き抜けの天井にシーリングファンを設置することは、空調効率を高めるための非常に効果的な対策です。
シーリングファンは、室内の空気を攪拌し、温度ムラを解消する役割を果たします。
夏場はファンの回転で気流を生み出し体感温度を下げ、冬場は天井付近に溜まった暖かい空気を床面へと送り届けることで足元の冷えを和らげます。
単なる扇風機とは異なり、空間全体の空気をゆっくりと循環させることが目的です。
デザイン性の高い製品も多く、おしゃれなインテリアのアクセントとしても機能するため、吹き抜けには必須のアイテムと言えるでしょう。
メンテナンスしやすい窓や照明器具を選ぶ

高所の掃除や電球交換といったメンテナンスの問題は、設計段階での工夫によって軽減できます。
例えば、吹き抜けの窓は、2階の廊下やキャットウォークから手が届く位置に設置すると、掃除が格段にしやすくなります。
また、電動で開閉できるタイプの窓を選ぶのも一つの方法です。
照明器具については、電球の寿命が非常に長いLEDライトを選ぶのが基本です。
壁付けのスポットライトにしたり、ワイヤーで吊り下げて高さを調整できるペンダントライトを選んだりすることで、交換作業の負担を減らす工夫ができます。
間取りを工夫して生活音や匂いの問題を軽減する
音や匂いの広がりは、間取りの工夫によってある程度コントロールすることが可能です。
例えば、寝室や書斎といったプライバシーを重視する部屋は、吹き抜けから離れた場所に配置するのが効果的です。
また、キッチンの匂いが気になる場合は、コンロの前に壁を設けたり、吹き抜けとの間に扉や引き戸を設置して空間を仕切れるようにしたりする間取りも考えられます。
高性能な換気システムを導入することと合わせて、生活動線や家族の過ごし方を考慮しながら、音や匂いが伝わりにくいプランを設計することが快適な暮らしにつながります。
吹き抜けに関するよくある疑問

吹き抜けの導入を検討していると、デザインや快適性以外にもさまざまな疑問が浮かびます。
「そもそも自分の暮らしに吹き抜けは本当にいるのか、いらないのか?」迷うこともあるかもしれません。
ここでは、そうした吹き抜けに関するよくある疑問について、分かりやすくお答えしていきます。
吹き抜けのある家は耐震性が低い?
吹き抜けを設けると床や壁が少なくなるため、建物の構造が弱くなり、耐震性が低くなるのではないかと心配する声があります。
しかし、現在の建築基準法では、すべての建物が定められたルールに基づき、厳しい耐震基準をクリアするように設計されています。
吹き抜けを作る場合は、その分、周りの壁を強化する壁量計算を行ったり、床の強度を高める水平構面を工夫したりして、建物全体の耐震性を確保します。
したがって、専門家が適切に構造計算を行い、正しく施工された家であれば、吹き抜けがあるからといって耐震性が著しく劣ることはありません。
吹き抜けを作ると建築費用が高くなる?
吹き抜けを作ると建築費用が高くなると思われがちですが、一概にそうとは言えません。
なぜなら、吹き抜け部分は2階の床を作らないため、その分の床材や下地材などの材料費、施工費はコストダウンになるからです。
ただし、吹き抜けを作ることで、工事中に室内足場が必要になったり、大きな窓や断熱性の高いサッシ、シーリングファン、デザイン性の高い照明などを採用したりすると、その分の費用は追加で発生します。
吹き抜け自体が高額になるのではなく、付随する仕様によって費用が変動すると考えるのが適切です。
おしゃれな吹き抜けの事例を場所別に紹介
吹き抜けは、取り入れる場所やデザイン次第で、住まいの表情を豊かに彩る主役になります。
例えば、天井に木の梁を見せて温かみのあるインテリアにしたり、壁の一部にアクセントとしてタイルやデザイン性の高い壁紙(クロス)を取り入れたりするのも素敵な例です。
ウッドデッキや庭など外の景色とのつながりを意識した横長の窓の配置など、理想の空間づくりのヒントがきっと見つかります。
ここでは、リビングや玄関、階段など、場所別に様々なおしゃれな吹き抜けの実例をご紹介します。
開放感あふれるリビングの吹き抜け実例

リビングは家族が集まる家の中心であり、吹き抜けを設ける場所として最も人気があります。
特にリビング階段と組み合わせることで、空間に一体感が生まれ、より一層おしゃれで開放的な雰囲気を演出できます。

大きな窓からたっぷりと光が差し込む明るいリビングは、日々の暮らしを豊かにしてくれるでしょう。
天井を高くすることで、背の高い観葉植物を置いたり、存在感のあるペンダントライトを吊るしたりと、インテリアコーディネートの幅も広がります。
縦の空間を活かしたダイナミックな空間づくりが楽しめるのが、リビングの吹き抜けの魅力です。
階段スペースを有効活用した吹き抜け実例

階段や廊下は、単なる上下階の移動スペースと考えられがちですが、吹き抜けと組み合わせることで、家全体のデザイン性を高める重要な空間に変わります。
特に、骨組みだけで構成されたスケルトン階段を採用すると、光と視線が通り抜け、空間の広がりをより一層感じさせます。

階段の壁面に大きな窓を設けて採光スペースとしたり、壁一面を本棚やアートを飾るギャラリースペースとして活用したりするのも素敵なアイデアです。
階段スペースを吹き抜けにすることで、上下階のつながりが生まれ、家全体に一体感と動きが生まれます。
明るくおしゃれな印象になる玄関の吹き抜け実例

家の顔とも言える玄関やエントランスホールに吹き抜けを設けると、訪れた人に開放的で明るい第一印象を与えられます。
限られたスペースでも、縦に視線が抜けることで圧迫感がなくなり、実際の面積以上に広く感じさせることが可能です。

高い位置に窓を設ければ、暗くなりがちな玄関ホールに自然光を取り入れ、常に明るい空間を保てます。
また、天井から吊るすデザイン性の高い照明器具を選べば、まるでホテルのロビーのような、おもてなしの空間を演出することもできます。
帰宅するたびに気持ちが華やぐような、特別なエントランスになります。
まとめ
吹き抜けは、2階建てや3階建てといった戸建て住宅に、平屋では得られにくい縦方向の開放感や明るさをもたらします。
家族のつながりを育む空間になるなど多くのメリットがある一方で、空調効率や音の伝わりやすさ、メンテナンスといった課題も存在します。
しかし、これらのデメリットは、高気密・高断熱な家づくりや、間取りの工夫といった対策を講じることで十分に解消が可能です。
ハーバーハウスでは、吹き抜けと鉄骨階段がセットになった商品「HARS」をご用意しております。
その他のプランに関しても、ご要望に合わせて吹き抜けのあるお家を実現することが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

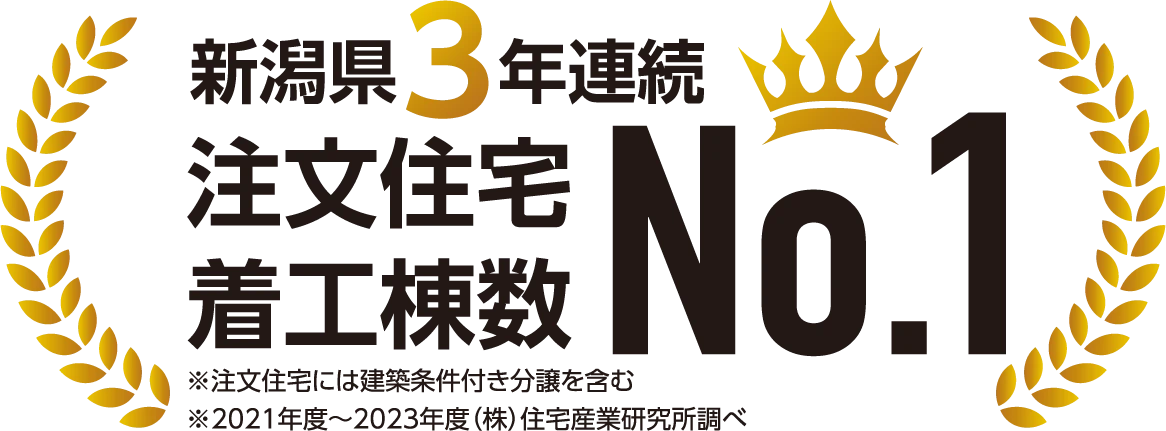
-1024x536.jpg)